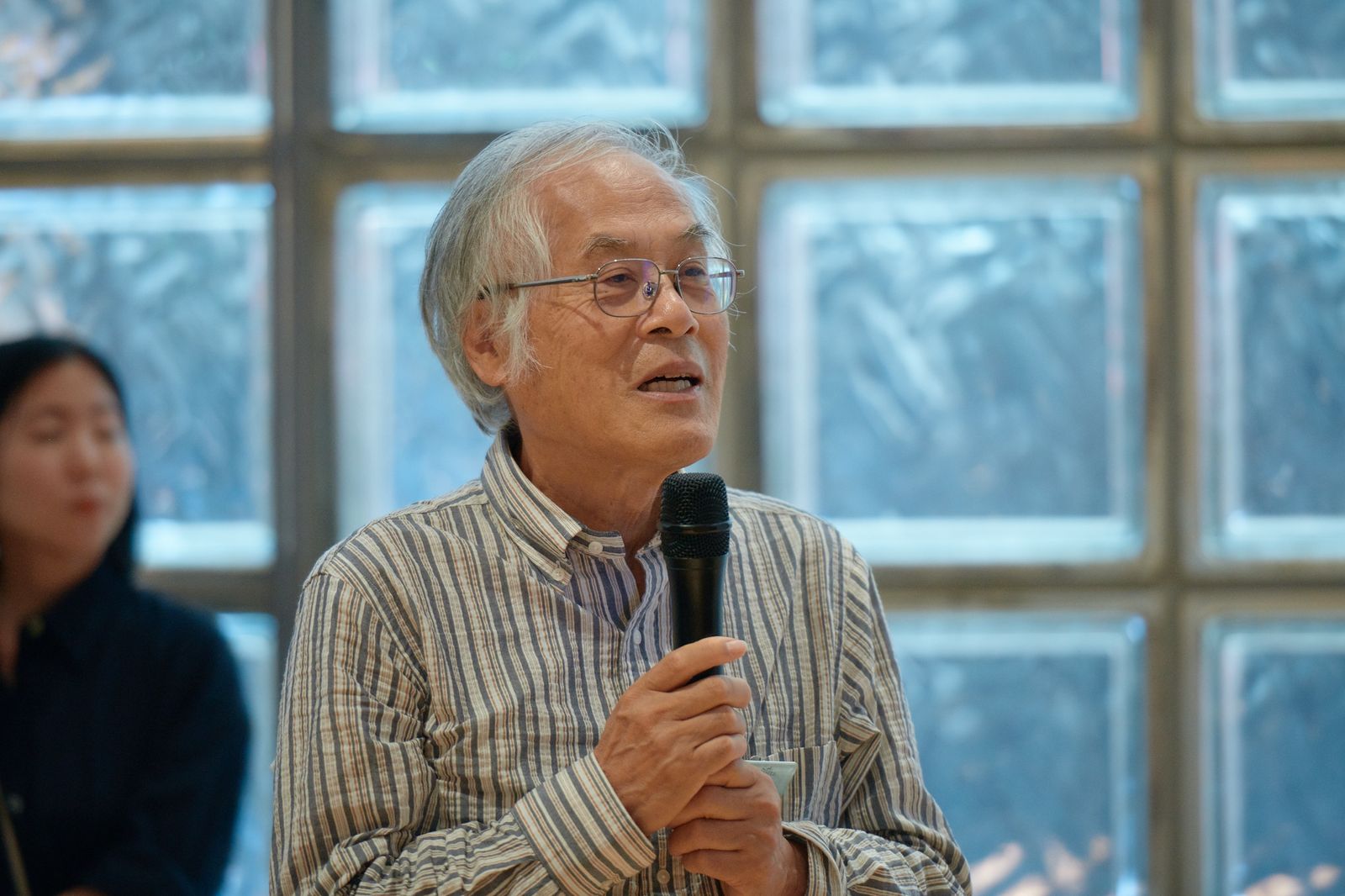銀座メゾンエルメス フォーラムで7月13日〜8月18日、エルメス財団が主催する「スキル・アカデミー」の「夏のオープンクラス」が開催された。
エルメス財団は、「エルメス(HERMES)」の出資によって2008年にパリで創設された非営利団体。「身振りが私たちをつくり、私たち自身の鏡になる」という理念のもと、「実践」や同ブランドを支える職人の「身振り」を大切にし、行動が周りや自分自身に与える影響を重んじたプログラムを展開する。
財団は芸術分野での「創造」、技術や手技の「伝承」、地球環境の「保護」、社会貢献を行う「連帯」という4つの分野を柱に活動しており、日本ではキュレーターの説田礼子氏のもと、「創造」の分野で現代アートのプログラムを、「伝承」の分野で「スキル・アカデミー」を実施する。
次世代へと繋ぐ社会貢献プログラム「スキル・アカデミー」
フランスでは14年から、日本では21年にスタートした「スキル・アカデミー」は、自然素材にまつわるスキルの伝承、拡張、知識の共有を目指すプログラム。「エルメス」の根幹にある職人技術やヒューマニズムの姿勢を学ぶ場であり、活動によって得られた集合知は、環境保護や社会貢献への眼差しにも結び付く。
2年ごとに一つの自然素材を選び、その素材を専門とする職人や研究者、アーティストたちを選出。分野を超えて知識や技術を共有し、その発展や伝承を広く試みる。日本版では21~22年は「木」を、23~24年は「土」をテーマとして取り上げた。
1年目は、テーマとなった自然素材の日本における受容やフランスとの比較、専門家の調査などを経て、書籍を出版。2年目となった今回は、アカデミーの創造性と学際性を次世代に伝えるべく、素材を異なる角度から体験し、その背景に広がる長い時間を理解できるような中高生向けプログラムを構成した。「日本では、受験勉強やクラブ活動に忙しく、学外の学びや自由な時間が持てない学生が多い。新たな出会いを通して、自己形成の最中で感受性豊かな中高生たちに、素材、技術、学びについて考えてほしい。重要なのは、実践的に関わることで身体知を獲得し、観察・鑑賞し、愛でること、表現を通して感性や美意識を養うこと、そして専門性を横断し学際的な学びを身につけること」と説田氏は語る。
今年3月に東京近郊で開催した、中高生向けの「春のワークショップ:土に学ぶ、五感で考える」にはインターネット公募で集まった約75名が参加。それぞれが「五感」——土に素肌で触れて感覚をひらく、その感触を詩やダンスで表現する、土の中の生態系やシステムを学ぶ、土を食材として味わう、縄文土器を手作りする、土の建築について学び、土壁づくりを実践する——を通して生物にとって最もプリミティブな存在の「土」について深掘りした。
「夏のオープンクラス」ではこの「春のワークショップ」で講師を務めた研究者やアーティストと共に、これらの体験と成果、土にまつわる学際的な知識とスキルを共有し、鑑賞者が土について学び、考え、新たな魅力を感じられる展示を作り上げた。中高生向けのワークショップを展示形式で一般公開するのは、エルメス財団にとって初の試みだ。
土の住居を手作りし、時間の経過を共にたどることで
サステナブルな視点を身につける
「夏のオープンクラス」は「春のワークショップの成果物と講師の作品」「ワークショップの学びを発展させた、新たなゲストを招いての展示物」という2要素で構成された。コンセプトは、土が素材から、人間の手でかたちになり、そして素材へ還るところまでを五感で体験し、味わうこと。会期を通して変化する学びの場で「土から離れた都市で暮らす人々に土を感じてほしい」と、説田氏は語る。
会場の中心には、建築史家であり建築家の藤森照信氏の監修のもと、土建築研究家の山田宮土理氏と左官職人の都倉達弥氏とともに、ワークショップ参加者が作り上げた「家としての建築」がたたずむ。鑑賞者は小さな扉から中に入ることもできる。人の手の痕跡があらわな文様状の壁面を、上から差し込む光が静かに照らす光景は、古代の祭壇を思わせる。
1 / 2
この建築について藤森氏は「土のみの建築には、異素材を組み合わせて作る建築にできる境目がないため、『目地』もできない。それは生物の細胞が境目なく内側から分裂していくことや、人間の身体や肌に似ている。今回作ったような泥だけで構成された建築は、世界でも事例が少ない。この建築の中に入ったときの、泥に包まれる感覚、泥の空間に光が落ちてくる感じを味わってもらいたい」と語った。
建築壁面に点在する陶器でできたチューブ状の穴は、ワークショップで講師を務めた陶芸家・西條茜氏によるもの。「フンデルトヴァッサーが『第3の皮膚』と言ったように、住宅は構造的にも身体になぞらえられる。壁面には、体の入り口にも出口にも見えるような不思議な質感の焼き物のチューブを埋め込んだ。そこに鑑賞者が建築の内外から息や声を吹き込んだり、音を響かせたりすることで、内と外が繋がることをイメージした」と西條氏は語った。
1 / 2
建築の正面には、同じく西條氏がサウンド・アーティストと共に制作した陶器製の彫刻作品《ホムンクルス》が展示された。土器と同じ「手びねり」の技法で作られたものだ。「土の造形物・パフォーマー同士の身体・空間が音を介してつながっていく瞬間を作りたい」との発想で、水牛の角のような形状の先端にある穴に息を吹き込むと、法螺貝(ほらがい)のようなサウンドが鳴り響く。「焼き物は土には戻らない。『地球の一部を使ってものを作ること』の責任と、『ものを作りたい』という人間の欲求。アートにはエコロジーとの関係性をリアルに思い巡らせる側面がある」と西條氏は考察する。
建築の周囲には実をつけたミニトマトなどの野菜の鉢が吊るされたり、木製のベンチに埋め込まれたりしており、間近で土と植物が紡ぐ生命の時間を感じることができる。植物が植えられた土は現代美術家の保良雄が石巻から運んできたもの。壁沿いには「春のワークショップ」で参加者が手作りした縄文土器と、多摩ニュータウン遺跡群から出土した本物の縄文土器、エチオピアで今も作り続けられている土器が並ぶ。
「春のワークショップ」で学術的に観察された土壌動物は、別のかたちで提示された。彫刻家・井原宏蕗氏は、ミミズの糞塚に金彩を施されたジュエリー“jewelry from earth-gold ring”を制作し、井原氏は犬や鳩のふんから動物をかたちづくる彫刻を生み出した。また、メディアアーティストの三原聡一郎氏の装置で春から継続的に作られるコンポストは、土・生物・環境の循環を想起させた。
今回の展示は、時間とともに建築の土壁にヒビが入ったり、周囲の植物が育ったりと、会期を通して変化していく。「土の建築は、手入れをしなくなったらどうなるのか」「最終的に、どんな形で土に還せるのか」という問いは、長い時間軸でのサステナブルな視点を持つことにつながる。会期終盤には、現代美術家の保良雄氏の公開制作と演出家/ダンサーの倉田翠氏のパフォーマンスが実施され、これらの問いが改めて検証された。
次回スキル・アカデミーは秋の特別プログラムとして、陶芸ワークショップ「土という技術について考えるⅡ」を開催予定。3日間にわたり東京藝術大学取手キャンパスにて土の採掘から作品の完成までを体験するもの。エルメス財団のウェブサイトで9月8日まで参加者を募集している。