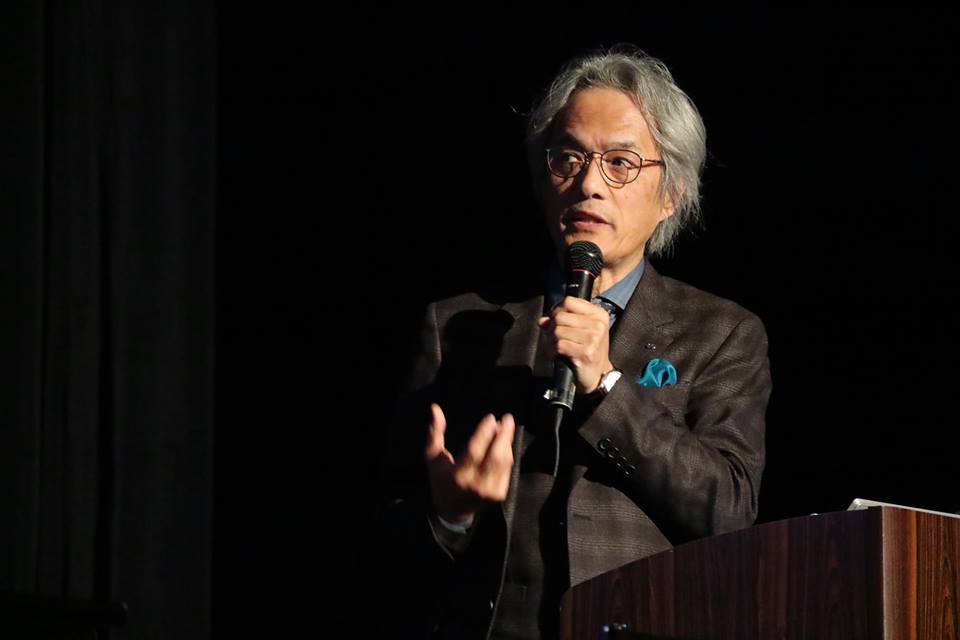早稲田大学ラグジュアリーブランディング研究所は1月31日、シンポジウム「日本の“こだわり”が世界を魅了する 〜2020年に向けて、日本の価値を考える〜」を大隈講堂で開催した。司会進行を長沢伸也・早稲田大学ラグジュアリーブランディング研究所所長/早稲田大学ビジネススクール教授が務め、車メーカーのレクサスインターナショナル、セレクトショップ大手のビームス、新潟県三条市を拠点とするアウトドアブランドのスノーピーク、富山県高岡市の伝統産業で鋳物メーカーである能作、そして経済産業省の各責任者を招いて、ブランディングにおける“こだわり”についてパネルディスカッションを実施した。
 長沢伸也・早稲田大学ラグジュアリーブランディング研究所所長/早稲田大学ビジネススクール教授
長沢伸也・早稲田大学ラグジュアリーブランディング研究所所長/早稲田大学ビジネススクール教授
長沢教授:まず初めに、日本ブランドの「強み」や「弱み」は何かを考えたい。
澤良宏レクサスインターナショナル エグゼクティブ・ヴァイスプレジデント(EVP):日本発の「レクサス(LEXUS)」は若いブランドなので、伝統的なブランドと比べて弱みを持っている。しかし弱みがある分、チャレンジャーとなって他のブランドとは違うことができ、それが強みになる。日本の匠の技やデザインがその一つだ。
山井太スノーピーク社長:品質でいうと、メード・イン・ジャパンは世界で一番いいものを持っている。しかし世界では、それが認識されていない。
長沢教授:私が考えるラグジュアリー・ブランドとは、バッグやジュエリーメーカーなどだけではなく、“高くても売れるモノ”や“熱烈なファンがいるモノ”だ。そうであれば欧州の老舗メゾンだけではなく、日本の地場産業などもそれに値する可能性は秘めている。
能作克治・能作社長:日本が作っているモノは間違いなく世界で一番だが、作り手がそれをアピールできずに謙遜してしまっている。欧米だと品質がイマイチでも「私たちは素晴らしいモノを作っている」と高らかに謳っており、プロモーションが上手い。
長沢教授:日本はプロモーションが弱いのか。その点を含めて、ビームスの場合はどう考えているのか。
 遠藤恵司ビームス副社長
遠藤恵司ビームス副社長
遠藤恵司ビームス副社長:日本はお客さまがクオリティの高いモノを求めているから、提供する側のクオリティも上がったと思う。例えば10万円の「オールデン(ALDEN)」のシューズのロゴが曲がっていたら、アメリカ人だったら気にしないかもしれないが、日本のお客さまは購入しない。だからこそ、こちらも高品質なモノを提供する努力をしている。
長沢教授:日本の地場産業は本質的には強いと思うが、さらに盛り上げるためには何が必要か。
中内重則・経済産業省製造産業局 伝統的工芸品産業室長(併)企画官(地場産品担当):長沢教授が考えるラグジュアリー・ブランドをラグジュアリーたらしめる構成要素「理念」「技術力(実現力)」「実行力」の3つは、地場産業を盛り上げるためにも重要なことだと思う。これらが備わっていれば、世界で通用するブランドになることは不可能ではない。
 中内重則・経済産業省製造産業局 伝統的工芸品産業室長(併)企画官(地場産品担当)
中内重則・経済産業省製造産業局 伝統的工芸品産業室長(併)企画官(地場産品担当)
長沢教授:今日のシンポジウムのサブタイトルに“2020年”とつけたのは、単に流行に乗ったわけではない。何をやるにせよ、東京五輪までは企業にとって追い風が吹くはずだ。登壇者の方々は東京五輪をチャンスと捉えているのか。
遠藤ビームス副社長:チャンスでないと思った方がいい。百貨店などでは爆買いに頼ったために失速した。今後、訪日外国人が増えても購買行動が変わる可能性もあるので、過度に期待するのは危ない。やるべきことをしっかりとやっていくべきだ。
中内経産省室長:五輪はチャンスだ。ただ、その先のビジョンも描くことが重要だ。五輪に焦点を当ててしまうと、五輪以降に困難な状況になりかねない。
長沢教授:日本企業は、誰がどのように“こだわり”を生むのか。先述した3つの構成要素も含めて意見を述べてほしい。
能作社長:こだわりを持つのは、それを好きになること。自分の作っているもの、自分の住んでいるところに対して、誇りを持つ環境づくりが大事だ。そうすることで、こだわりが生まれる。自分たちに自信がないと海外でも堂々と渡り合えないと思う。
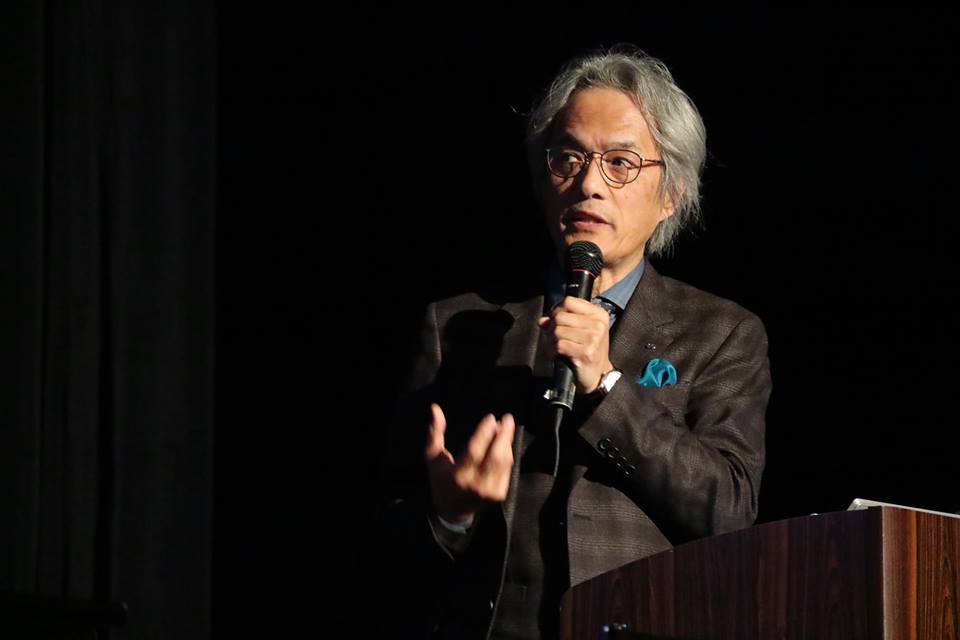 澤良宏レクサスインターナショナル エグゼクティブ・ヴァイスプレジデント
澤良宏レクサスインターナショナル エグゼクティブ・ヴァイスプレジデント
澤レクサスEVP:「レクサス」は世界中に生産拠点があるので、しっかりとした理念がないといけない。こだわったモノ作りをした後は、理念に沿ってプロモーションしていく必要がある。理念を軸に常にレベルアップしていかないと、世界に誇れるブランドは作れない。デザインは大切だが、あくまでこだわりの一つで走りの性能やクラフツマンシップ、技術も重要だ。
山井スノーピーク社長:こだわりの根底にあるのは、理念とミッションだと思う。誰を幸せにするのか?どう幸せにするのか?ということが大切だ。これを突き詰めなければ、いいモノは作れない。
長沢教授:デザインに“こだわる”場合は、誰がデザインすべきなのか。社内なのか、あるいは外部なのか。地場産業でも外部デザイナーの力を借りて躍進しているところが目立つが、デザインについての考え方を教えてほしい。
中内経産省企画官:産地の人が自分たちの強みや弱みを認識していないことがあるので、外部デザイナーは有用だと思う。外からの知恵を借りるのも一つの手だ。
遠藤ビームス副社長:ビームスには特定のデザイナーがいない。デザインにおいて専制的な人がいると、トレンドから外れていても保身に走るので危ないと思う。モノ作りはストリート目線、お客様目線で進めなくてはならない。デザイナーという肩書きがなくても、モノに対して好きな気持ちがあればよく、むしろそちらの方が面白いモノができたりする。
長沢教授:能作社長は自らデザインもしているが。
能作社長:外部のデザイナーを産地に派遣してもらって、勉強会を開いていた時があった。そこでは、生産者はデザイナーに対して“先生”と呼んでいた。しかしデザイナーと生産者は本来、対等な立場でなければならない。弊社では現在、20人くらいのデザイナーを雇用しており対等に接している。
澤レクサスEVP:基本的には世界各国にいるインハウスのデザイナーを使っている。フィロソフィーやコンセプトに沿ったオリジナルデザインを採用しているが、最終的には本部で日本人が仕上げている。外国人のデザインを採用しても、日本人によって仕上げるのが「レクサス」のフィロソフィーであるからだ。
 山井太スノーピーク社長
山井太スノーピーク社長
山井スノーピーク社長:デザインは全て社内で行う。今まで世の中にないものを作ることが弊社のミッションだ。その実現のために、例えばアウトドア製品を作るならば、アウトドアが好きで、クリエイティビティがあって、(本社所在地の)燕三条の町工場を熟知している3in1のような人間を社内で育成する必要がある。
 能作克治・能作社長
能作克治・能作社長
長沢教授:ブランドとして成功するには何が重要か。
中内経産省企画官:実行力が大事で、特に熱意を強く感じる人が成功している。成功を継続させるのは企画力も重要だ。
遠藤ビームス副社長:会社のオリジナリティをどう発信するか。確かに外部には優秀なデザイナーはたくさんいるが、ビームスならビームスの匂いがプロダクトに乗っているかが大事。外部に委託して、オリエンテーションを重ねたとしてもビームスらしくはならない。
澤レクサスEVP:モノ作りは技術がないと実現できない。生産技術の向上だけでなく、デザイナーやエンジニアが切磋琢磨してモノ作りが良くなっている。デザイナーがデザイン画を描いて、モノを作っているだけではブランドは作れない。ライフスタイルにも目を向けなければいいモノは作れない。
長沢教授:私は“並外れた人の普通のモノが、普通の人の並外れたモノになる”ということがラグジュアリーだと考える。では、“並外れた人”とは誰か。例えば「シャネル(CHANEL)」というブランドは、創業者ココ・シャネル(Coco Chanel)という絶対的な存在がいる。さらに“並外れた顧客”もブランドにとっては重要で、例えば「カルティエ(CARTIER)」では、発明家であり飛行家のアルベルト・サントス=デュモン(Alberto Santos-Dumont)という顧客がいた。サントス=デュモンからスペシャル・オーダーされた一点モノの時計を、「カルティエ」は“サントス”として一般販売した。「ジャガー・ルクルト(JAEGER-LECOULTRE)」の“レベルソ”という時計は、文字盤をひっくり返すことができる。これは、ポロ競技をやるときにガラス面が割れないようにするためだが、これは貴族からの要望を受けて作ったモノだ。このように特殊な顧客から要求されたモノを一般に売るということもある。
遠藤ビームス副社長:ファッションにとってストーリーやバックグラウンドは重要。例えば映画「ティファニーで朝食を」で主演を演じるオードリー・ヘプバーン(Audrey Hepburn)は「ジバンシィ(GIVENCHY)」を着ていた。特に男性はうんちくが好きで、ファッションではそれが顕著だと思う。
長沢教授:日本企業はうんちくを作ることは得意か。
能作社長:私たちのような伝統産業は本来、うんちくを作りやすい。先ほどの話にあった“こだわり”については、全てに適用していると単なる頑固になってしまう。モノ作りにおけるこだわりとは、極めること。全部じゃなくてほんの少しでも極める意識があるかどうかが、こだわりではないのか。食の話になるが、私もカレーを一から作るとか、ベーコンを2週間かけて作るとか、そのようなこだわりが多い。仕事に対するこだわりも同じなのかもしれない。
長沢教授:日本の地場産業や伝統産業はうんちくを持っているようだが、それは“知る人ぞ知る=知らない人は知らない”ものになっているのではないか。
中内経産省企画官:それは私たちのPR不足でもあるので、今後しっかりと取り組んで行きたいと思っている。例えば京都の西陣織は5〜6世紀からある。今の時代はいい技術でいいモノを作るだけでは売れないので、伝統産業もストーリーをアピールしていかなくては。
澤レクサスEVP:例えば葛飾北斎やアニメは、海外で評価されようと思って作っていなかった。しかし、誰かが海外に紹介した時に初めて評価された。その“誰か”が目利きとして、日本のいいモノを見出すことが大切で、そこで初めてブランドとして評価されると思う。
長沢教授:ラグジュアリー戦略においても目利きは重要だ。“知る人ぞ知る=知らない人は知らない”では困るから、ターゲットではない顧客にもアピールする必要がある。
遠藤ビームス副社長:本当に感度の高い人は、市場ではわずかしかいない。その下にオピニオンリーダーのような立場の人がいて、マスに影響を与える。マスも一様ではなく、無関心な層もいる。対象が200人でも3万人でも同じような割合で、そのヒエラルキーが存在する。ビームスでは、オピニオンリーダーに徹底的にアピールする。オピニオンリーダーより上の層にアピールするのは、数が少なく、間口が狭いために難しい。オピニオンリーダーから段々とマスに浸透させる。マスから流行ったモノをオピニオンリーダーが身に付けることはないから、最初からマスを狙うことはしない。必ず上からスパイラル状に落とし込んでいくことが重要。モノが流行る過程は必ずそうなっている。
山井スノーピーク社長:「スノーピーク」はハイエンドなアウトドアブランドを目指している。弊社の場合だと、創業者である父(山井幸雄)が山登りをしている写真を掲載しており、自らがユーザーとしてモノを作っていることをアピールしている。会社が誰を幸せにするブランドかということで、ストーリーの作り方は違ってくると思う。
長沢教授:現代はモノが溢れている。競争が激しくなるにつれ、結果としてモノが同質化してしまう。そのような状況では、消費者はモノを選ぶことができない。消費者がモノを選ぶ時には、合理的でなくても購入に至る際に“理由”が必要。その理由こそ、これまで話してきた“こだわり”が一番なじみやすい。時間がなくて話すことができなかったが、こだわりを生むための人材が必要だ。そのために是非とも早稲田大学のビジネススクールへの入学し、勉強していただきたい(笑)。